誰かと共に、諦めず
SAHO(小6)
私は友達が机に向かってため息をついているのを見かけた。手元の課題がうまく進まないのか、顔には困ったような表情が浮かんでいる。そんな友達を見て、私はすぐに声をかけた。
「どうしたの?」
友達は少し驚いた顔をしてから、ぽつりと言った。
「うーん、この問題がどうしても解けなくて、もう諦めた方がいいのかなって思ってるんだよ…」
私は少し考えてから、静かに隣の席に座り、友達のノートを覗き込んだ。
「あ~この問題は少しややこしいよね、前に似たような問題を解いたことあるよ!まずは、どこでつまずいたのか、一緒に確認してみるか!」
友達は少し戸惑いながらも、
「本当に?」
と顔を上げた。私は頷き、ゆっくりと問題を解く手順を説明し始めた。私が丁寧に説明していくと、友達もだんだんと笑顔を取り戻し、途中で
「なるほど!」
と声を上げた。
「ありがとう、すごく助かったよ。ちょっと自信が出てきた気がする!」
その言葉を聞いたとき、私も嬉しくなった。友達が少しでも元気を取り戻したことが、何より嬉しかったからだ。私は 「いつでも手伝うからね!」
と笑顔で答え、そのまま教室に戻った。やっぱ人を助けると自分まで気分がいいな!

解説
「誰かを励ましたり、元気づけたりした場面を書いてください。」という課題に対して書かれた作文です。
「私は少し考えてから、静かに隣の席に座り、友達のノートを覗き込んだ。 」の一文を読んだ時に、なるほど!と感心しました。今回課題を出す際に、誰かを応援したり励ましたりする時、どうすればいいと思うか考えて欲しいと伝えてありました。この場面、流れの中で主人公の動きを自然に書いているようでいて、実はSAHOさんの考える応援の仕方が表現されています。仮に、(静かにでなく)大きな声で話しかけてきたら、(隣にでなく)向かい合うように座っていたら、まるで違う空気になり、果たして友達は素直に助けを受け入れられたでしょうか。寄り添い、同じ方向を見て、一緒に進もうというメッセージが感じられからこそ、素直に教えを乞うこともできたのではないでしょうか。さりげないですが、とても多くのことを表現している一文だと思いました。
実はこの作文、実話とフィクションを織り交ぜて書かれているそうです。「本当は助けられたのが私なんだよね」とSAHOさん。つまり、助けられた側でありながら、助けた側の主人公の立場で作文を仕上げたということです。それだけに助けられる友達の心の動きが実に繊細に描かれています。「困ったような表情が浮かんでいる」「少し驚いた顔をしてから、ぽつりと言った」「顔を上げた」「だんだんと笑顔を取り戻し」。これらを通して、困り顔→驚き→顔を上げる→笑顔、というように段々と元気を取り戻していく変化が丁寧に描かれているのです。さらに面白いことに、正解はないと言って出した課題だったにも関わらず、この作文においては、主人公の励まし方は大正解だということが保証されています。何せ、助けられた本人がそう認めているのですから。
上から目線で助けるのではなく、隣に来て一緒に進んでくれる、SAHOさんの考える応援のスタイル、素敵です。読んだ後、自分の応援の仕方についても考えさせられる一作でした。
塾長
オンライン作文教室のUEDA学習塾であなたも作文を始めてみませんか?
© 2025 UEDA学習塾. 無断転載を禁じます。

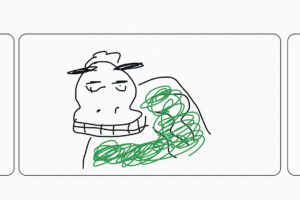
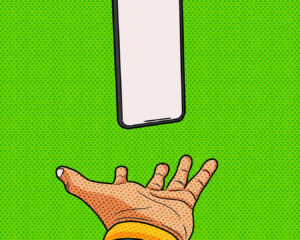
これを書いたのが実体験からなんてすごいですね。作文、解説共々、読んで心が温まりました。